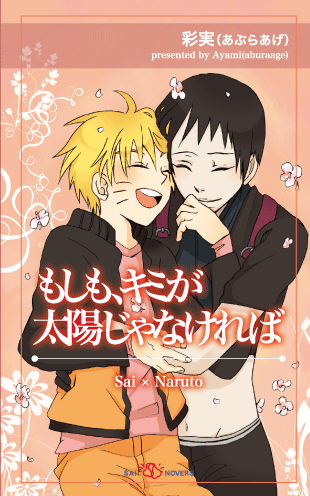
「にんじんとジャガイモと…あとリンゴも下さい」
微かに笑みを浮かべながら、サイは食料貧店の店主に告げた。
恰幅のいい女店主は、にこにこしながらサイが頼んだ者をビニールの袋に詰める。
「リンゴ、一個おまけしておいたよ」
店主にそう言われ、差し出されたビニールの中を見ると、リンゴが一つ多く入っていた。ここに来る度にリンゴを買っていたので、すっかり店主に覚えられてしまったらしい。
ほんのり顔を染めながら礼を言い店の外へ出ると、上着についているフードを目深に被った。
道を歩きながら空を見上げると、太陽が沈みかけていた。燃え尽きるみたいに赤く染まる太陽を見て、サイは急いで家路につく。
おそらく家に帰る頃には太陽はすっかり沈んでしまっているだろう。
商店がある街から、サイが住んでいる家は遠い。
うっそうとした森の中に、同居人と二人で暮らしている。この世に存在する誰よりも、サイ自身よりも大事な人間と一緒に。
リンゴをおまけしてくれた女店主の顔がふと頭を過ぎる。
顔を覚えられてしまった。
被っているフードを、さらに深くかぶり直す。外にいるときはなるべく顔を隠して歩いているが、店の中ではそうはいかない。
リンゴの件自体は嬉しかったが、顔を覚えられてしまったのは非常にまずい。手に提げている袋に入ったリンゴのことを思い出しながらサイは森へ入る。
昼間でも日の光があまりささないこの森は、夕暮れどきになるともう真っ暗だ。
忍びであるサイには大した事のない道のりだったが、普通の人間は昼間でもあまりこの森には近づかない。
だからサイはこの森の奥に住むことを選んだ。自分はともかく、同居人を人目にさらすわけにはいかない。彼はあまりにも目立つ容姿をしている。
誰にも森に住んでいることを知られてはいけない。赤の他人はもちろん、サイやその同居人が以前親しくしていた人間にもだ。
顔を覚えられてしまったのなら、また別の街に移動したほうがいいかもしれない。
誰かにここに住んでいることが知られたら、守って上げられない。逃げて、ここに隠れさせるだけで精一杯だった。
もっと力があれば、と時折サイは悔やむこともある。力さえあれば、こんなところに閉じこめるようにして隠させずに済んだのに。
だが、悔やんでも今はどうすることもできない。
今できることは、少しでも長く、誰にも見つからないようにすることだけだ。
家が見えてきて、サイは足を速めた。こんな風に外にいる間は、同居人のことが気になって仕方が無い。
ふと家の窓を見ると、暗くなっているのに明かりがついていなくて心臓が大きく脈打った。
それに気づいた瞬間、サイは気配を消し、辺りの様子を窺う。人が大勢やってきたような形跡は見当たらない。
足音を立てないように窓の方へ移動し、中の様子を窺ってみるが、家には誰もいなかった。
とりあえず、ほっと息をつくものの、同居人がいないことは明白だ。
探しに行こうと、サイは来た道を戻ろうとした。
「サイー!」
呼ばれて振り向くと、土まみれの顔をした少年がサイをめがけて書けてくるのが見える。
辺りはもう暗いはずなのに、走ってくる少年の姿が妙にまぶしく感じられて、思わず目を細めた。
「ナルト!」
名前を呼び、サイも少年の方へ駆け寄った。
叱られるとでも思ったのか、ナルトと呼ばれた少年はびくっと体を震わせる。
「ケガとかしてない?」
顔に付いていた土を拭ってやりながら、問いかけると、ナルトは小さく頷いた。
「暗くなったら外に出ちゃダメだって言ったよね?」
「ごめんってば。探検してたらいつの間にか暗くなってて…」
しゅんとした様子で言い訳をするナルトに、サイは仕方なさそうにため息をついた。
ナルトなら、いくらサイが言い聞かせても森の中を探索したり、街へ降りたりしたがるだろうとは思っていた。自分がやると決めたことは、周りもなにも顧みず遂行する。いいことであれ、悪いことであれ。
その行動力がサイにとってはうらやましいものだった。
例え今、ナルトのこれまでの記憶がなくても、それは変わらない。
昔を思い出すように、ナルトを見つめた。
「……サイ?」
黙ったまま見つめていたのを不審に思ったのか、不思議そうな顔をしてナルトが名前を呼ぶ。
「…何でもないよ。もう家に入ろう。少し肌寒くなってきた」
ナルトの手をとって、二人で家に入った。真っ暗な部屋に明かりを灯し、サイは二人分、温かいお茶を入れると、テーブルに座って待っているナルトにひとつ差し出す。
砂糖とミルクを多めに入れて飲むのがなるとの好みだ。
「やっぱりサイの淹れるお茶は最高だってばよ」
「褒めても、なにもでないよ」
「なぁなぁ、今日の夕飯なに?」
「カレーだよ。あとお店の人がリンゴ一つおまけしてくれたからデザートの他にサラダにでも淹れようかと思ってるけど」
「ラーメンがいいってばよ」
ラーメン、ラーメン、と騒ぐなるとにサイは苦笑を漏らす。こんなところも記憶を失う前と変わらない。安心すると同時に、罪悪感がサイの胸の中に生まれる。
ナルトが記憶を失ったのは自分のせいだ、とサイは思っている。記憶と引き替えに命を救えたとしても、元を辿れば自分が任務を優先したせいだ。
「ごめん、ナルト」
「え?別にそんなに気にしてないってばよ…?ラーメンは食べたいけど、カレーも大好きだってばよ!」
落ち込んだように謝る自分に、ナルトは慌てて早くカレーが食べたいとアピールし始める。本当はラーメンが食べたいに決まっているのに。
ごめん、ともう一度心の中で呟いた。もしも、任務を優先しなければ、もしも、逃げ出したあの里が、ナルトにとってもう少し優しいものだったら、もしも――ナルトと出会っていなければ。
きっとナルトは大好きな一楽のラーメンをいつでも食べられていたのに、と『もしも』を考えるとキリがない。
そんな考えを振り払うように、サイは頭を振り、ナルトに笑みを向ける。
つくりものみたいだとナルトに言われた笑顔は、少しは自然に浮かべられるようになっただろうか。
「カレー出来るまで少し時間がかかるから、リンゴでも食べて待っててよ」
ビニール袋からリンゴを取り出して渡すと、ナルトはごしごしと表面を袖で拭き、がぶりと勢いよくかぶりつく。
「食べたら、お風呂の準備だけしてもらえる?」
「んー」
もぐもぐとリンゴを咀嚼しながら、ナルトから生返事が帰ってくる。あっという間にリンゴを食べ終わると、慌ただしく風呂の方へ向かっていった。
